


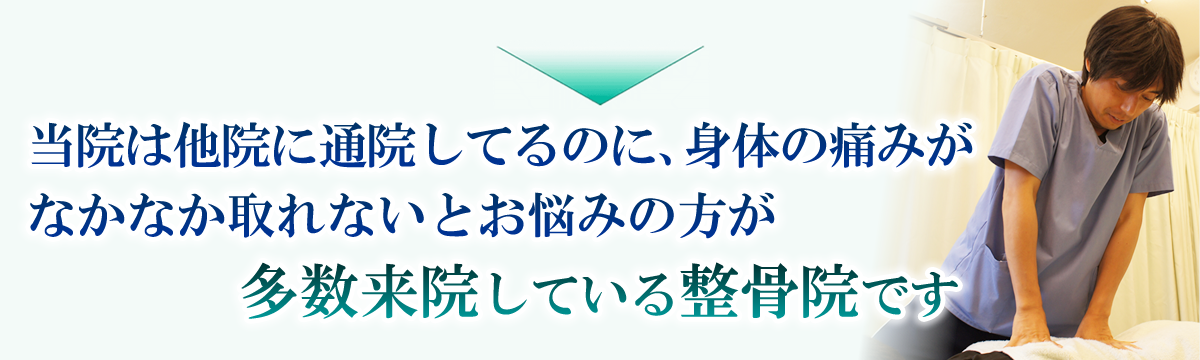
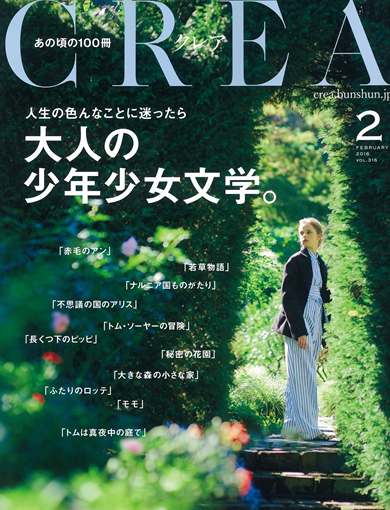
『CREA 2016年2号』

『Ray 2016年2号』
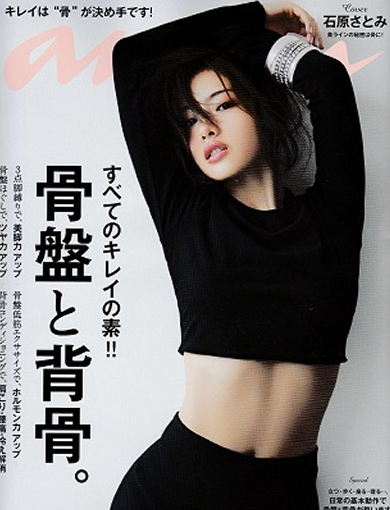
『anan 2015年10月21日号』

『ひよこクラブ 2016年1月号』
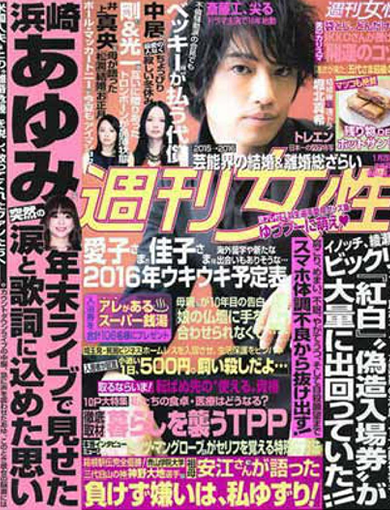
『週刊女性 2016年1月26日号』

『腰痛に効く!全国治療院ガイド』
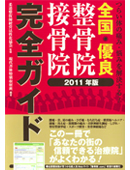
『全国優良整骨院・接骨院ガイド2011年版』

『すてきな奥さん』
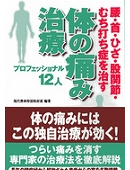
『体の痛み治療・プロフェッショナル12人』
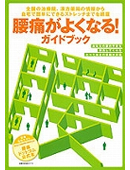
『腰痛がよくなる!ガイドブック』


「レントゲンでは異常なしと言われたのに、膝の痛みが治らない」
「湿布や電気治療を続けているけど、膝痛がぶり返す」
このような悩みを抱えて来院される方は、実は少なくありません。
整骨院の現場で多く見られるのが、膝そのものではなく“骨盤のズレ”が原因となっている膝痛です。
本記事では、
について、整骨院の視点から詳しく解説します。
膝関節は、
の間に位置し、上半身の体重と動作の衝撃を受け止める中継点です。
そのため、
のバランスが崩れると、最も負担が集中しやすいのが膝になります。
整骨院で膝痛の方を診ていると、次のような共通点が見られます。
これらはすべて、骨盤の歪み・ズレが影響して起こる動作の乱れです。
骨盤は、
という、下半身全体の土台の役割を担っています。
この骨盤がズレると、
結果として、膝への負担のかかり方が左右で変わってしまいます。
骨盤が傾いた状態で歩いたり立ったりすると、
が本来の軌道から外れやすくなります。
すると、
「曲げ伸ばしはできるけど、特定の角度で痛い」
「階段の下りだけがつらい」
といった、原因が分かりにくい膝痛につながります。
膝が痛いと、
を行うケースが多いですが、これだけでは一時的に楽になるだけで終わることが少なくありません。
理由はシンプルで、
膝に負担をかけ続けている原因(骨盤のズレ)が残っているからです。
このループに入ってしまうと、
「なかなか治らない膝痛」
「年齢のせいと言われる膝痛」
になりやすくなります。
骨盤矯正というと、
「強く押す」「音を鳴らす」
といったイメージを持たれがちですが、整骨院では
を総合的に評価しながら、身体に負担の少ない矯正を行います。
整骨院では、膝痛の方に対して次のような点を確認します。
これらを確認することで、
「なぜこの膝に痛みが出ているのか」
が明確になります。
骨盤が正しい位置に近づくと、
ようになり、膝が無理に頑張らなくて済む状態になります。
結果として、
といった変化を感じる方が多くなります。
膝痛対策として筋トレを勧められることもありますが、
骨盤がズレたまま筋トレをすると、逆に膝痛を悪化させるケースもあります。
整骨院では、
という順番を大切にしています。
これらに当てはまる場合、
膝ではなく骨盤が原因の可能性を一度疑ってみる価値があります。
膝痛があると、どうしても膝そのものに目が向きがちですが、
実際には
といった全身バランスの崩れが深く関係しています。
整骨院では、
「痛いところだけを見る」のではなく、
なぜそこに負担が集中したのかを重視します。
もし、膝痛がなかなか改善しないと感じているなら、
一度「骨盤」という下半身の土台から身体を見直してみてください。
それが、膝痛改善への近道になるかもしれません。
「姿勢を意識しているのに、首や肩がつらい」
「ストレートネックと言われてから、逆に違和感が増えた気がする」
このような悩みを抱えて、整骨院に来院される方は少なくありません。
実は、ストレートネックと姿勢改善は“正しい順番”で行わないと、うまくいかないことが多いのです。
本記事では、
を、体の構造と動きの視点から分かりやすく解説します。
ストレートネックとは、
本来ゆるやかなカーブを描いている首の骨(頸椎)が、まっすぐに近い状態になっていることを指します。
このカーブには、
という重要な役割があります。
一見、首だけの問題に見えますが、実際には全身の姿勢バランスに影響します。
ストレートネックの人がよく行うのが、
といった姿勢意識です。
しかし、首の土台が崩れた状態でこれを行うと、
👉 首・肩・背中の筋肉に余計な緊張が生まれます。
結果として、
「姿勢を意識するほどつらい」
という状態に陥ってしまうのです。
姿勢改善とは、
意識でキープするものではなく、無意識で保てる状態を作ることです。
ストレートネックがあると、
ため、正しい姿勢を維持するために筋肉が頑張り続けてしまいます。
首は背骨の一番上にあり、
その位置が崩れると、背骨全体でバランスを取ろうとします。
この連鎖が続くことで、姿勢改善をしても元に戻りやすい体になってしまいます。
ストレートネックがある状態で、
といったアプローチをしても、首の位置が変わらなければ再発します。
整骨院では、いきなり「姿勢を良くしましょう」とは言いません。
まず行うのは、
の評価です。
ストレートネックの場合、
首にかかっている負担を減らすことが最優先になります。
首だけでなく、
を整えることで、首が無理なく正しい位置に戻れる環境を作ります。
最終的な目標は、
「意識しなくても姿勢が崩れにくい体」
これができて初めて、
ストレートネックと姿勢改善が両立します。
顎を引く意識が強すぎると、
首の後ろが常に緊張し、逆にストレートネックを助長することがあります。
胸を張ることで一時的に姿勢が良く見えても、
実際には腰や首を反らしているだけのケースも多く見られます。
大切なのは、
首を無理に正しい位置に固定することではなく、
動かせる首を取り戻すことです。
正しい姿勢は、
体が正しく使えるようになった“結果”として現れるもの。
ストレートネックを放置したまま姿勢だけ直そうとすると、
不調は長引きやすくなります。
「姿勢を意識しているのに楽にならない」
「ストレートネックと診断されて不安」
そんな方こそ、
姿勢を直す前に、体の使い方を見直す視点が必要です。
整骨院では、ストレートネックを含めた全身バランスを評価し、
無理なく姿勢が整う体づくりをサポートしています。
「マッサージを受けても腰痛がすぐ戻る」
「ストレッチをしているのに、腰が軽くならない」
このような慢性腰痛に悩む方は非常に多く、整骨院にも日々相談が寄せられます。
しかし実際の施術現場では、腰痛が長引く人ほど腰そのものに大きな異常がないケースも少なくありません。
整骨院で注目するのは、
👉 “お尻(殿筋)の硬さ”
本記事では、
を、体の構造と動きの視点から詳しく解説します。
慢性的な腰痛に悩む方の多くが、
といった腰への直接アプローチを行っています。
それでも改善しないのは、
👉 腰が「原因」ではなく「結果」になっている
可能性が高いためです。
腰は、
を常に受け止める部位です。
本来その負担を分散する役割を担っているのが、お尻の筋肉です。
お尻の筋肉(殿筋群)は、
といった日常動作の中心となる大きな筋肉です。
この筋肉がしっかり使えていれば、
腰は必要以上に頑張らずに済みます。
意外に思われるかもしれませんが、
お尻が硬い人ほど、お尻の筋肉がうまく使えていません。
使えない → 動かない → 血流低下 → 硬くなる
この悪循環が続くと、腰が代わりに働き続けることになります。
デスクワークや車移動が多い方は、
お尻の筋肉を長時間圧迫したままの状態になります。
この状態が続くと、
結果として、お尻はどんどん硬くなっていきます。
こうした動作習慣も、お尻の筋肉をサボらせる原因です。
これらのタイミングで腰痛が強く出る人は、
お尻の筋肉が動作に参加できていない可能性が高いです。
お尻が働かない分、
腰の関節や筋肉に負担が集中し、動かした瞬間に痛みが出やすくなります。
整骨院では、腰痛のある方に対して、
を総合的にチェックします。
その中で多く見つかるのが、
👉 お尻の筋肉が働いていない状態 です。
お尻が原因の場合、
といった特徴が見られます。
マッサージで筋肉を緩めても、
体の使い方そのものが変わらなければ、また同じ負担がかかります。
特にお尻が使えない状態では、
腰はすぐに元の頑張りすぎ状態に戻ってしまいます。
腰痛を改善するには、
が正しく連動して動く状態を作ることが重要です。
お尻の筋肉が働くためには、
骨盤と股関節がスムーズに動く必要があります。
整骨院では、
を整えながら、お尻が自然に使える状態へ導きます。
お尻が使えるようになると、
といった変化が現れます。
慢性腰痛ほど、
👉 原因は腰以外にある
ケースが非常に多いです。
自分では気づきにくい
お尻の硬さ・使えていなさこそ、
腰痛改善のカギになります。
「腰ばかり治療しているのに良くならない」
「もうこの腰痛と一生付き合うしかないのか…」
そう感じている方こそ、
お尻という視点を取り入れてみてください。
整骨院では、腰痛を“結果”として捉え、
その原因となる体の使い方まで丁寧に整えていきます。
「肩も腰も両方つらい」
「肩こりがひどくなると、なぜか腰痛も悪化する」
このように肩こりと腰痛が同時に出ることで悩んでいる方は、整骨院では非常に多く来院されます。
実はこの2つの不調、偶然同時に起きているわけではありません。
肩こりと腰痛は、体の歪みが連鎖して起こる代表的な症状です。
本記事では、なぜ肩こりと腰痛が同時に現れるのか、そのメカニズムを整骨院の視点から詳しく解説します。
肩こりは肩、腰痛は腰と、
それぞれ場所が違うため「別の問題」と考えがちですが、
整骨院では同じ原因から派生しているケースを多く見ています。
その共通点が、
です。
人の体は、
首 → 肩 → 背中 → 腰 → 骨盤
と一続きにつながっています。
どこか一部が崩れると、
その影響は上下へと広がり、肩こりと腰痛が同時に起こる状態になります。
本来、体は動作や姿勢を取る際に
負担を全身で分散する仕組みになっています。
しかし体が歪むと、
といった偏りが生じ、
結果として肩や腰に負担が集中します。
体の歪みは、
など、日常の無意識な癖の積み重ねで作られます。
この歪みが、肩こりと腰痛を同時に引き起こします。
背中が丸くなると、
頭が前に出て首や肩に大きな負担がかかります。
同時に、
ため、腰痛も起こりやすくなります。
この姿勢はデスクワークの方に非常に多いパターンです。
一見姿勢が良さそうに見える反り腰も、
肩こり・腰痛が同時に出やすい状態です。
腰を反らせて立つことで、
結果、腰痛と肩こりがセットで現れます。
肩や腰を揉んで楽になるのは、
一時的に筋肉の緊張が緩むからです。
しかし、
体の歪みや使い方が変わらなければ、
肩こり・腰痛はすぐに再発します。
強いマッサージを繰り返すことで、
筋肉が硬くなり、歪みを助長するケースもあります。
整骨院では、
「なぜそこに負担が集中しているのか」
を重視します。
整骨院では、
歪みを「ここが悪い」と一点で考えません。
これらが連動して崩れている状態を
「歪み連鎖」と捉えます。
骨盤は体の土台です。
骨盤が傾いたり不安定になると、
バランスを取るために背骨や肩が歪み、肩こりが起こります。
同時に、土台が不安定なため腰痛も生じます。
肩こりだけ、腰痛だけを施術しても、
体の歪み連鎖が残っていれば改善は限定的です。
そのため整骨院では、
肩・腰を同時に評価し、
体全体のバランスを整える施術を行います。
施術では、
ことで、肩や腰に負担が集中しない体へ導きます。
無理に姿勢を正そうとすると、
肩や腰に力が入り、逆効果になることがあります。
大切なのは、
楽に支えられる姿勢を作ることです。
こうした日常動作を見直すことが、
肩こり・腰痛の同時改善につながります。
肩こりと腰痛が同時に出るのは、
体が発している重要なサインです。
そんな方ほど、
体全体の歪みと連動に目を向ける必要があります。
整骨院では、
肩や腰だけでなく、
体全体を一つのつながりとして診ることで、
根本改善を目指します。
「もう年だから仕方ない」と諦める前に、
一度ご自身の体の歪み連鎖を見直してみてください。
「肩を揉んでも、すぐ肩こりが戻る」
「マッサージ直後は楽なのに、翌日にはつらい」
このような慢性的な肩こりに悩む方は非常に多く、整骨院にも日々多くの相談が寄せられます。
しかし、その多くの方が見落としているポイントがあります。
それが 「骨盤の状態」 です。
本記事では、
を、体の構造から分かりやすく解説します。
肩こりがなかなか改善しない人には、次のような共通点があります。
これらはすべて、骨盤の不安定さと深く関係しています。
肩は、頭と腕を支える重要な部位ですが、
その土台となるのは 背骨と骨盤 です。
骨盤が傾いたり、左右差がある状態では、
体はバランスを取ろうとして上半身に無理な力を使います。
その結果、
👉 首・肩周りの筋肉が常に緊張
👉 血流が悪くなり、肩こりが慢性化
という流れが生まれます。
骨盤は、
という 姿勢の土台 の役割を担っています。
この土台が傾くと、家の基礎が歪むのと同じように、
背骨全体がバランスを崩します。
骨盤が前後・左右に崩れると、次のような連鎖が起こります。
この状態では、いくら肩をほぐしても、
原因が解消されないため再発してしまいます。
このタイプは、背中の筋肉が過剰に使われ、肩こりが慢性化しやすくなります。
肩甲骨が動きにくくなり、首・肩の血流が悪化します。
左右の筋肉バランスが崩れ、片側だけ肩こりが強く出るケースも少なくありません。
マッサージは、
という点では有効です。
しかし、骨盤の歪みや姿勢のクセが残ったままだと、
体はすぐに元の使い方に戻ってしまいます。
肩こりの根本原因は、
👉 肩が頑張りすぎる体の使い方
骨盤が不安定な状態では、
上半身が無意識に姿勢を支え続けるため、肩こりは繰り返されます。
整骨院で行う骨盤矯正は、
単に「骨を鳴らす」「形を整える」ものではありません。
を総合的に評価し、体が正しく使える状態を作ることを目的とします。
骨盤が安定すると、
結果として、
👉 肩こりが起こりにくい姿勢
へと変化していきます。
肩こりに悩む方ほど、
「肩だけをどうにかしよう」
と考えがちです。
しかし実際には、
まで含めて見直すことが、改善への近道です。
骨盤を整えることはゴールではなく、
👉 正しい姿勢を維持できる体づくりのスタート
整骨院では、施術だけでなく、
日常動作・座り方・立ち方まで含めてアドバイスを行います。
「何をしても肩こりが良くならない」
「その場しのぎのケアから卒業したい」
そう感じている方は、
肩ではなく骨盤から見直す視点を持つことが、改善への第一歩です。
整骨院では、肩こりを“結果”として捉え、
その原因となる体の連鎖を丁寧に整えていきます。
「姿勢を意識するようにしたのに、腰痛が良くならない」
「猫背は直ってきた気がするのに、腰の重だるさが残る」
このような悩みを抱えて来院される方は、整骨院では決して少なくありません。
実はその多くに共通しているのが、姿勢改善はできていても“骨盤の使い方”が変わっていないという点です。
本記事では、なぜ姿勢改善しても腰痛が残るのか、
そして整骨院がなぜ「骨盤の使い方」に注目するのかを、専門的な視点で分かりやすく解説します。
多くの方が「姿勢改善」と聞くと、
といった見た目の修正をイメージします。
しかし整骨院の現場では、
見た目が良くなっても腰痛が残るケースを数多く見てきました。
その原因は、姿勢を支える体の使い方が変わっていないことにあります。
姿勢を意識しすぎると、
といった状態になり、かえって腰痛を悪化させることもあります。
これは、骨盤がうまく使えていない状態で姿勢だけを整えようとする典型例です。
骨盤は、
をつなぐ体の中心です。
この骨盤が安定し、適切に動くことで、腰への負担は分散されます。
逆に骨盤の使い方が悪いと、
その影響は真っ先に腰へ現れ、腰痛として感じやすくなります。
骨盤というと「歪み」をイメージする方が多いですが、
整骨院では動きの少なさを重視します。
こうした状態では、腰が代わりに動かされ続け、慢性腰痛につながります。
本来、
といった動作は、骨盤や股関節が主役です。
しかし腰痛がある方は、これらの動きを腰だけで行う癖がついています。
姿勢を正しても、動きの癖が変わらなければ腰痛は残ります。
骨盤を安定させるためには、
といった筋肉の連携が必要です。
これらがうまく働かないと、姿勢を維持するために腰周りの筋肉が頑張り続ける状態になります。
腰痛対策として、骨盤周りのストレッチを行う方は多いですが、
柔らかくするだけでは十分ではありません。
重要なのは、
動作の中で骨盤が正しく使われているかです。
お尻や体幹が「使えていない状態」のままでは、
ストレッチ後もすぐに元の動きに戻ってしまいます。
その結果、
のに腰痛が残る、という状態に陥ります。
整骨院では、骨盤を
「固める」「締める」
ものとは考えません。
重要なのは、
というメリハリのある使い方です。
腰痛と姿勢改善を目的とした施術では、
次のような点を確認します。
これらをもとに、腰に負担を集中させない体作りを行います。
骨盤が正しく使えるようになると、
姿勢は「頑張って作るもの」ではなくなります。
結果として、
といった変化が起こり、腰痛も軽減しやすくなります。
骨盤主導で動けるようになると、
歩く・座る・立つといった日常動作そのものが
腰痛を悪化させにくい動きに変わります
整骨院が重視するのは、
一瞬の正しい姿勢ではなく、
日常で繰り返される体の使い方です。
姿勢改善と腰痛改善を同時に叶えるには、
骨盤を中心とした体の連動を整えることが欠かせません。
これらを見直すことが、次の一歩になります。
姿勢改善しても腰痛が残る場合、
問題は努力不足ではありません。
注目すべきは骨盤の使い方です。
この2点が整うことで、
姿勢は自然に安定し、腰痛も再発しにくくなります。
「姿勢は良くなったのに腰がつらい」
そんな方こそ、一度整骨院で
骨盤の使い方と体の連動をチェックしてみてください。
「階段の上り下りで膝が痛い」
「歩き始めや立ち上がるときに膝に違和感が出る」
そんな膝痛に悩む方を整骨院で診ていると、意外な共通点が見えてきます。
それが、お尻の筋肉がかたいという点です。
膝が痛いのに、なぜお尻が関係するのでしょうか?
本記事では、「お尻がかたい人に多い膝痛の正体」と「下半身の連動」という視点から、整骨院がどのように膝痛を捉えているのかを詳しく解説します。
膝は体重を支え、歩行や階段動作で大きな負荷がかかる関節です。
そのため、痛みが出ると「膝が悪い」と考えがちですが、実際には負担を受けた結果として痛みが出ているだけのケースが多くあります。
整骨院では、
「なぜ膝に負担が集中しているのか?」
という視点で体全体を評価します。
膝関節は、
に挟まれた位置にあります。
そのため、股関節や足首の動きが悪くなると、膝が代わりに頑張らされる構造になっています。
お尻(殿筋群)は、
といった動作で、体を前に進めたり支えたりする重要な筋肉です。
本来、下半身の動きはお尻が主役となって行われます。
お尻がかたくなると、股関節の動きが制限されます。
すると、本来股関節で吸収・分散されるはずの負担が、膝へ流れてしまいます。
これが、
「お尻がかたい人ほど膝痛が起こりやすい」
大きな理由の一つです。
お尻や股関節が十分に動かないと、
を膝が過剰に担当することになります。
この状態が続くと、
といった膝痛につながります。
お尻がかたい人は、
といった癖が出やすくなります。
これらの動作も、膝への負担をさらに増やします。
膝が痛いと、
を行う方が多いですが、これだけでは改善しないケースが多くあります。
理由は明確で、
負担を生み出している「お尻のかたさ」が残っているからです。
単純に筋肉が硬いだけでなく、
という状態になっていることも少なくありません。
その場合、伸ばすだけでは機能は戻りません。
整骨院では、膝痛を
下半身の連動が崩れているサイン
として捉えます。
具体的には、
がスムーズにつながって動いているかを確認します。
お尻の筋肉は骨盤と大腿骨をつなぎ、
下半身全体の動きをコントロールしています。
そのため、
状態では、膝への負担が避けられません。
整骨院では、膝痛の方に対して
膝だけを集中的に施術することはほとんどありません。
を整えることで、結果的に膝の負担を減らします。
施術では、
といった流れを重視します。
これが、膝痛の再発予防にもつながります。
長時間座り続ける生活は、お尻を硬くする大きな要因です。
お尻が使われない時間が増えるほど、膝への負担は増えていきます。
こうしたサインがある場合、
すでに下半身の連動が崩れ始めています。
膝痛があるからといって、原因が膝だけにあるとは限りません。
お尻がかたい状態が続くことで、膝が無理をさせられているケースは非常に多くあります。
そんな方こそ、
お尻と下半身全体の連動に目を向けてみてください。
整骨院では、痛みのある膝だけでなく、
体全体の動きとバランスを見ながら根本改善を目指します。
「膝が悪いから仕方ない」と諦める前に、
一度お尻のかたさと下半身の使い方をチェックしてみてはいかがでしょうか。
「マッサージしても肩こりがすぐ戻る」
「首が重く、肩までガチガチに固まる」
このような不調を抱えている方の多くに共通して見られるのがストレートネックです。
ストレートネックというと「首の問題」と思われがちですが、実は首だけでなく背骨全体のバランスが深く関係しています。
本記事では、なぜストレートネックが肩こりを悪化させるのか、その仕組みを整骨院の視点から詳しく解説します。
正常な首(頸椎)は、横から見ると緩やかなカーブを描いています。
このカーブがあることで、頭の重さ(約5〜6kg)を分散し、首や肩への負担を軽減しています。
しかし、
が続くと、首のカーブが失われ、ストレートネックの状態になります。
整骨院の現場では、年齢を問わずストレートネックの方が増えています。
ストレートネックになると、頭が体より前に出た状態になります。
この姿勢では、首から肩にかけての筋肉が常に頭を支え続ける状態になります。
結果として、
が過剰に働き、慢性的な肩こりが起こります。
ストレートネックは首だけの問題ではありません。
首のカーブが崩れると、背骨全体のバランスが連鎖的に崩れます。
こうした変化が重なり、肩こりがさらに悪化していきます。
ストレートネックの方の肩周りの筋肉は、
リラックスする時間がほとんどありません。
本来、
を繰り返すことで筋肉は回復しますが、姿勢が崩れた状態では常に緊張したままになります。
筋肉の緊張が続くと血流が悪くなり、
が起こります。
これが「重だるさ」「張り感」として感じる肩こりの正体です。
肩を揉んで楽になるのは、あくまで結果に対する対処です。
ストレートネックという根本原因が残っていれば、肩こりはすぐに戻ります。
整骨院では、
「肩がつらい=肩だけの問題」
とは考えません。
首と背骨の位置関係が変わらなければ、
同じ筋肉に同じ負担がかかり続けます。
そのため、
だけでは根本改善に至らないケースが多いのです。
整骨院では、ストレートネックだからといって首だけを調整することはありません。
重要なのは、
首は背骨の一部であり、全身の連動の中で整える必要があります。
施術では、
ことで、首や肩に過剰な負担がかからない体へ導きます。
「姿勢を正そう」と無理に意識すると、
首や肩に力が入り、かえって肩こりを悪化させることがあります。
大切なのは、
正しい姿勢を“自然に保てる体”を作ることです。
肩こりが続く方は、次の点を見直してみてください。
こうした小さな積み重ねが、ストレートネックと肩こりを招いています。
ストレートネックは、
肩こりを引き起こすだけでなく、慢性化させる大きな要因です。
首と背骨の関係を正しく整えることで、
といった変化が期待できます。
「長年の肩こりだから仕方ない」
そう諦める前に、一度ストレートネックと背骨のバランスをチェックしてみてください。
整骨院では、首だけでなく全身を見たアプローチで、根本改善を目指します。
「肩をほぐしても、すぐに肩こりが戻る」
「マッサージ直後は楽だけど、翌日には元通り」
このような なかなか取れない肩こりで悩んでいる方は非常に多く、整骨院にも日々多く来院されます。
そして体を詳しくチェックしていくと、肩や首とは**一見関係なさそうな“お尻の硬さ”**が見つかるケースが少なくありません。
実は、お尻がかたい状態は、肩こりが慢性化する大きな原因の一つなのです。
この記事では、
を、現場目線で分かりやすく解説します。
肩こりがあると、多くの方は
といった肩周辺だけのケアを行います。
もちろん一時的な緩和にはなりますが、
それでもすぐに戻ってしまう場合、本当の原因は別の場所にある可能性が高いです。
整骨院では、
だけでなく、
なぜそこに負担が集中したのかを重視します。
肩こりが慢性化している方ほど、
肩以外の場所に大きなヒントが隠れています。
お尻には、
といった、体を支える重要な筋肉が集まっています。
これらは、
といった日常動作の土台となる筋肉です。
整骨院の現場で多いのは、
によって、お尻の筋肉が
固まってしまうケースです。
お尻の筋肉が硬くなると、
骨盤の動きが制限されます。
骨盤は背骨の土台です。
この土台が動かないと、背骨全体の連動が崩れます。
骨盤がうまく使えないと、
その結果、
肩や首がその分を補おうとして過剰に働くようになります。
これが、
肩をほぐしても取れない肩こりの正体です。
本来、体は
という役割分担があります。
しかし、お尻が硬いと、
支える役割を肩が担うようになり、
常に緊張状態になります。
お尻が硬い方ほど、
姿勢がクセになっています。
この状態では、
背中から肩にかけて負担が集中します。
無意識に、
こうしたクセも、
お尻の硬さと肩こりを助長します。
整骨院では、肩こりを
として捉えます。
その中でも、
お尻と骨盤の状態は必ずチェックする重要ポイントです。
お尻がしっかり使えるようになると、
その結果、
肩や首は無理に頑張らなくて済む状態になります。
これが、
「肩を触っていないのに楽になる」理由です。
整骨院では、
を通して、
どの部分が、どの動きで硬くなっているかを確認します。
いきなり肩をほぐすのではなく、
の動きを回復させます。
これが肩こり改善の土台になります。
最終的には、
姿勢を目指します。
肩に力を入れなくても、
自然と楽な状態が作れるのが理想です。
最近は「お尻ストレッチ」も多く紹介されていますが、
では改善しないこともあります。
動かす順番や姿勢を間違えると、
逆に腰や肩を痛めることもあります。
こうした方は、
お尻を含めた全身連動が崩れている可能性が高いです。
肩こりが取れない原因は、
必ずしも肩そのものにあるとは限りません。
お尻の硬さ → 骨盤の不安定 → 背骨の連動不全 → 肩こり
という流れは、整骨院ではよく見られます。
肩だけを追いかけるのではなく、
全身のつながりから見直すことで、
肩こりは大きく変わる可能性があります。
慢性的な肩こりでお悩みの方は、
一度、整骨院視点で「お尻の状態」もチェックしてみてください。
「マッサージを受けてもすぐ腰痛が戻る」「ストレッチや体操を続けているのに改善しない」
このような慢性腰痛に悩む方は非常に多く、整骨院の現場でも毎日のように相談を受けます。
実はその多くに共通しているのが、**腰そのものではなく“姿勢の問題”**です。
本記事では、なぜ腰痛が慢性化する人ほど姿勢改善が必要なのかを、整骨院の視点から詳しく解説します。
腰痛というと、多くの方が「腰の筋肉が硬い」「骨が歪んでいる」と考えがちです。
しかし実際には、腰は結果として痛みが出ているだけというケースが非常に多くあります。
肩や股関節、背中、骨盤などの動きが悪くなることで、
本来分散されるはずの負担が腰に集中し、痛みとして現れているのです。
湿布・痛み止め・マッサージだけでは、
「一時的に楽になる → また痛くなる」を繰り返します。
これは、負担を生み出している姿勢や動作が変わっていないためです。
慢性腰痛の背景には、必ずといっていいほど姿勢の崩れが存在します。
猫背・反り腰・骨盤の前傾や後傾といった姿勢の乱れは、
立っているだけ、座っているだけでも腰にストレスをかけ続けます。
特に現代人は、
により、無意識のうちに腰へ負担のかかる姿勢を取り続けています。
姿勢が崩れると、
が生まれます。
腰周りの筋肉だけが常に頑張る状態になり、疲労が抜けず腰痛が慢性化します。
「背筋を伸ばす」「良い姿勢を意識する」
これ自体は悪くありませんが、体の準備ができていない状態で行うと逆効果になることがあります。
無理に姿勢を正そうとすると、
といった状態になり、かえって腰痛が悪化するケースも少なくありません。
姿勢改善には、
が不可欠です。
これらが整っていない状態では、正しい姿勢を「保つ」こと自体が難しいのです。
整骨院では、姿勢を「見た目」だけで判断しません。
重要なのは、
といった体の使い方の癖です。
姿勢は、体の機能が整った結果として自然に良くなるものです。
慢性腰痛の方に対して、整骨院では次の点を重視します。
これらを総合的に評価し、腰に負担を集中させない体作りを行います。
腰痛が続くと、無意識に痛みを避ける姿勢を取ります。
その結果、さらに姿勢が崩れ、負担が増えるという悪循環に陥ります。
このループを断ち切るには、
腰だけを見るのではなく、姿勢全体を見直す必要があります。
一時的に痛みが取れても、姿勢が変わらなければ再発します。
姿勢改善は、腰痛を「治す」だけでなく、
繰り返さない体を作るための重要な要素です。
慢性腰痛に悩む方ほど、
を見直す必要があります。
腰痛と姿勢改善は切り離せない関係です。
体の土台から整え、正しい姿勢が自然に保てる状態を作ることが、
慢性腰痛から抜け出す近道となります。
「何をしても腰痛が改善しない」
そんな方こそ、一度整骨院で姿勢と体の使い方を総合的にチェックしてみてください。
| 受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前9:00~12:30 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 午後13:00~17:00 ※予約優先 |
休診日 |
| 午後15:00~20:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 平日受付 | 午前9:00~12:30 午後13:00~17:00 |
|---|---|
| 土曜受付 | 午後13:00~17:00 ※予約優先 |
| 休診日 | 日・祝 |